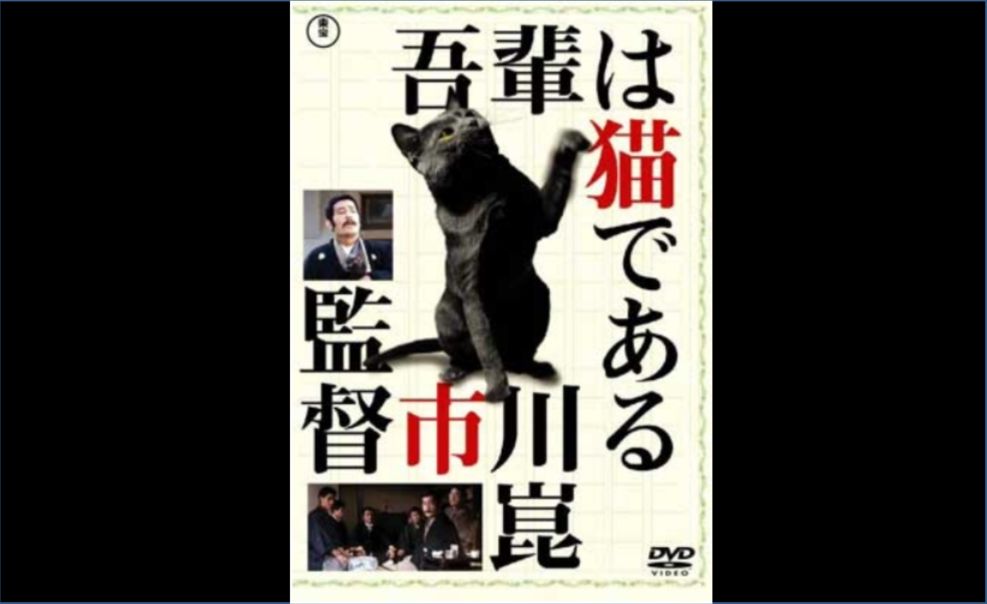
俗物のおしゃべり
俗物とは、世間に漂う人だ。自らの信念を持たず、常に空気を読む。「吾輩は猫である」は、夏目漱石が俗物を風刺した小説である。
中学教師の仲代達矢は、妻(波乃久里子)と三人の子供と共に、雨漏りのする安普請の家に暮らしている。この家に、さして用件もなく訪れる伊丹十三、岡本信人、前田武彦、篠田三郎。俗物たちは、愚にもつかないことをのんべんだらりと喋っている。波乃は、夫と来訪者を少し軽蔑しながらも、受け入れている。
女性の俗物陣は、男性より攻撃的だ。実業家(三波伸介)の妻(岡田茉莉子)と娘(篠ひろ子)、琴の師匠(緑魔子)は、仲代を痛烈に皮肉り、こきおろす。男性陣と女性陣が交わることはあまりないが、唯一直接対決するシーンがある。
岡本と篠の縁談が持ち上がりそうな気配を見て、岡田は、岡本を良く知る仲代を訪ねる。偶然居合わせた伊丹も含めた女1対男2の戦いは、岡田の圧勝に終わる。
特に面談の内容に勝ち負けがあるわけではないが、岡田の迫力は名優二人を大いに圧している。この縁談は整うことなく、篠は左とん平と婚約するのだが。
俗物たちのおしゃべりは、あまりポジティブには傾かず、社会の在り様を批評する。誰かの悪口で溜飲を下げる。こうした風潮は、明治も令和もさしてかわりない。
男優の競演
主演の仲代達矢は、煮え切らない人物を巧みに演じる。煮え切らなさに仲代独自の軽妙な味がある。「殺人狂時代(1967)」が想起される。しかし、「鍵(1959)」、「他人の顔(1966)」、「女王蜂(1978)」のように怜悧な人物を演じる際も、仲代にはどこか、なよなよとした質感が混ざっている。
本作での仲代は、校長に反抗したり、近隣の中学生に篭絡されたり、姪(島田陽子)の入浴姿にドギマギしたり、いかにも幼い。しっかり者の波乃に助けられて、なんとか家族を成立させているのだろう。
伊丹十三は、本人のキャラクターに近いスノッブなインテリだ。「妹(1974)」が想起される。頻繁に仲代邸を訪れるが、特に目的などない。単細胞の仲代に気の効いたツッコミを刺すのが愉しいのか。特に目的もなく漂ってはいるが、世間知や教養は深く、頭のよさそうな人物。仲代と伊丹の掛け合いは相性良く、名優二人のコラボによる名人芸を堪能できる。
校長を演じる岡田英次は、戦後復興期の日本映画を支えたスターだが、いかつい顔つきには、異形の怖ろしさが宿っている。単なる中学校の校長ではなく、何か大きな悪事を企んでいる男かのようだ。「君よ憤怒の河を渉れ(1976)」の精神病院の院長がそうであったように。
女優の競演
1975年は、もうテレビ時代になっており、テレビ出身の俳優も多かったが、そんななか映画俳優の貫禄を見せるのが、岡田茉莉子だ。当時42歳の岡田だが、18歳のデビューから百数十本の映画に出演し、成瀬巳喜男、小津安二郎といった巨匠の薫陶を受けた大女優の存在感は、唯一無比である。
和服の着こなしも堂々たるものだが、着物が象る女性らしい身体の曲線には、熟れた官能もある。若々しい美しさでいえば、27歳の篠ひろ子や22歳の島田陽子には適わないが、年輪を重ねた女の強さと弱さを、貫禄十分に体現している。
岡田と篠の母娘は、いかにも意地悪そうだが、そのとおり、篠は常に不貞腐れているような女だ。裕福な家に産まれたことや、自らの美貌を迷いなく鼻にかけている。
しかし、篠のような意地悪な女は、仮面の裏では男のストレートな愛情を切望している。茫漠とした岡本より、実行家の左を選んだのも首肯できる。
島田陽子は、この映画で唯一俗物でない人物だ。人の悪口など決して言わず、慎ましやかに朗らかな娘。往々にして映画はこうして美人を引き立たせる。彼女の美貌はまさに完璧だが、その声も美しい。高く透き通った声は、俗物たちを超越して、清冽に宙を行き交う。
金田一シリーズへの布石
翌1976年から市川崑監督の金田一耕助シリーズが始まったが、一作目「犬神家の一族(1976)」のヒロインが島田陽子だ。ここでも島田は、遺産相続と色欲に蠢く俗物一族のなかで、超然と清純さを貫いている。更に「吾輩は猫である」の島田と共通するのは、見え隠れする、したたかさだ。彼女は吉永小百合のような妖精ではなかった。
仲代達矢は4作目「女王蜂」に出演した。「吾輩は猫である」の中学教師とは違い、遠謀の野心家を演じたが、少し芝居がかった振舞いは本作を部分的に踏襲している。岡本信人は、すっとぼけた芸風を更に洗練させ、神山繫は浮薄にインチキな男を独自に造形した。
市川崑は、日本家屋の撮影に磨きをかけた。「吾輩は猫である」の仲代邸は、裕福ではない教師の家として、明治人の質素な生活を彷彿させる。文化財に指定される建築でなくても、日本の普通の家屋は、光と闇を存分に孕み、木材の朽ちていくさまにも独特の風合いがある。電灯の照度が低い明治には、部屋の隅々まで光は到達せず、自然の闇が残存していた。闇には、虫や小動物が蠢いており、人間だけの棲み処ではなかった。そんな家屋に、猫はのっそりとやって来る。
「獄門島」、「病院坂の首縊りの家」に登場する旧家。「悪魔の手毬唄」の山村の鄙びた旅館。金田一シリーズに忍び寄る血縁と因襲は、これら趣深い日本家屋を舞台に猟奇殺人へと変化するのだ。
スタイリッシュな構図とカッティング
猫のナレーションは、ラストの溺死シーンのときだけ発せられる。映画「吾輩は猫である」は、猫の眼から見た滑稽な人間をそれほど描かず、あくまで人間を主体に展開する。
猫は、少女的に可愛らしい存在とは見なされていない。市川崑は、猫の眼を通す、といった原作の構図を捨象し、力量高い俳優たちの伸び伸びとした演技を強調した。素晴らしいパフォーマンスは独自のアンサンブルを産み出し、一級のコメディーは現在にまで時代性を超えている。
この会話劇は、ほとんど仲代邸で繰り広げられるが、このような密室劇の場合、長回しと長台詞の演劇的スタイルを採る監督が多い。しかし、市川の真骨頂は、鋭いカッティングだ。目まぐるしくカットされた、遠近の構図。短く曖昧な返事の応酬。会話の長さについて人間の生理の持続する長さは、LINE程度なのだ。
会話の主役が脚本家ならば、構図の主役は撮影監督であり、映像のリズムの主役は編集者だ。静止画をベースとして遠近の妙味を撮影し、観客が飽きる寸前でスパッとカットする。市川崑最大の魅力である、スタイリッシュな構図とカッティングの切れ味は、ここでも存分に発揮されている。
明治と令和
明治こそ、激動の時代だった。変化のスピードは令和の比ではない。明治維新以降、政治体制も大衆文化も大幅に変貌した。ついこの前まで、ちょんまげを結っていたのだ。しかし、庶民の生活の心持ちは、そうそう変わるものではない。日本人は争いを好まず、積み重ねられた常識を無意識に踏襲し、呑気に暮らしていたし、今でもきっとそうだろう。
緊急時代宣言は常態化し、特に「緊急」ではなくなっている。政府の対策は大いに矛盾を孕んでいるのだが、人々は、感染の恐怖や過剰な自粛のなかで、それら全てをひっくるめてコロナ禍を受け入れている。日本人は冷静だが呑気なのだ。自らの信念など特にない。文句を垂れながらも、世間の風潮をなぞって、ルーチンをこなして生きている。仲代家や仲代邸に集まる人々が皆マスクをしていても、違和感はない。















LEAVE A REPLY